アウェアネスって調べてたら自己啓発(?)の記事ばっかでITの文脈での記事があんまなかったので書いてみました。(英語と学術にはありましたが)
一貫して上手くまとめれませんでしたが、例などでわかりやすくなっていると思うのでご容赦ください。
「**アウェアネス」は「**を知らせる」「**に関する周知方法」みたいな感じです。
Group Awareness
作業を効率的に遂行するために、現在のグループのプロセスや作業対象に関する情報を、グループ内のユーザ同士で相互に取得することを指す概念。
「Group Awarenessがちゃんとしている」→作業者間で情報(Aさんは手が空いている。器具Xは20分待ち。今、Bさんが作業Sを完了した。みたいな情報)が上手くシェアされている
という感じです。
実例(VideoWindow)
大型スクリーンで遠隔オフィス間を結び、24時間画像を流し続け、社員間のコミュニケーションを潤滑にした。
たまにニュースで見る、「教師不足の学校とかと別の学校を大画面映像で繋げて、1人の先生が複数の学校に授業同時配信」ってやつもこれに近いですね。「配信先の学校では教科書読んでもらって、進捗をメールして、、」みたいにするとめちゃめちゃ非効率なので、リアルタイムで同期した方がGroup Awarenessがいいですよね。(無理矢理用語ねじ込んだ感が否めませんがw)
Context(Contextual) Awareness
context(contextual) awarenessとは
ハードウェアやITシステムが、環境または操作のコンテキストに関する情報に基づいてユーザーの要求に応えることを指す概念。イメージ:コンテキスト(文脈を)アウェアネス(知覚する)
例えば、
・現在地位置情報(どこにいるかというコンテキスト)によって近くの飲食店とかを表示するサービスに組み込まれている
・腕時計型の体調測定するやつも、脈など(デバイスの環境のコンテクスト=人間から読みとっている情報)をもとに、消費カロリーとかを出力している
・たまに耳にする「用を足したら、健康診断してくれるトイレ」も、Context Awarenessが使われていますね
センサーとかで、ユーザの行動の文脈情報(誰が、いつ、どこで、何をしているか)を収集して、それを利用するってことですね。
参考

Workplace Awareness
Workplaceはここでは「職場」だけでなく「共同作業空間」というイメージで使われています。
Workplace Awareness=共同作業空間で他の人の進捗状況などがすぐ分かるかどうかを指す概念
という感じです。
例えば、パワポとかで、1つのパワポ資料に対して複数人で制作できるやつ。「田中さんが今ここの行を編集しています」みたいな表示されます。(イメージ:https://ckeditor.com/collaborative-editing/)
「なんらかの特定の作業を想定しているケース」
利用している全ユーザに対して同じ画面を表示するようなアプリケーションを目指してる。ユーザ間でお互いの進行状況に対する認識が共有され、ユーザはグループ全体の成果を意識しながら作業できる。
「特定の作業に目的を絞らないケース」
映像や音声によって、離れている場所にいる同僚と時間と空間を共有することによって、同じ部屋にいるのと同じ効果を生み出すことを目的にしている。通常の遠隔会議支援システムと違い、長時間利用を想定していて、仕事とは直接関係ない会話なども支援し、それらが生産性の向上につながることを期待している。
の2つに大別できる。
Social Awareness
構造的な気づきは、仮想学習コミュニティで行われるコミュニケーションを支援することを目的としています。
協調的な相互作用を促進するために、参加者にグループ構造を周知する。
Peripheral Awareness
Peripheral:周辺の
人間の知覚の周辺の情報を扱います。
例えば
・ラインの通知が来たら音が鳴って気づく
・画面にバーナーが表示される
・目覚まし時計が鳴る
足音が聞こえたら「あ、誰か来てるな」と分かるように人間には元々知覚機能が備わっているので、それを活用していろんな情報に気づいてもらうわけです。
「それとなく分かるように」情報をくれるので、ユーザは新しい情報を受け取っても現在の作業から気をそらす必要がないとされます。(けど、集中するときは通知全部切るよね)
危険アウェアネス
「不快な」インタフェースにより、ユーザに危険そうな行為を避けてもらう。
危険であろうサイトに遷移する前に、「〜〜〜ですが、リンク先に遷移しますか?」みたいな確認をさせることによって「なんか嫌だし、手間だからやめよ」ってなるのを狙っている。
他にも、不快な音(「ビロン!」みたいな)を出すことによって作業をためらってもらうこともある。(昔のWindowsとかこんなイメージありますが、最近のPCとかはあんまない気がします。設定すればできるでしょうが。)
Situation Awareness
シチュエーションアウェアネスは、意識に関わる研究の文脈で使われる用語。
自動運転など日常の判断・行動の場面でも適用が進んでいる。情報にアクセスし、その情報を行動のコントロールに利用できる状態のこと。
「あ、向こうから車来てるからこのままだとぶつかっちゃう」みたいな。
- 知覚:何が起こっているのか知る
- 理解:どうして起きているのか理解する
- 予測:このままにするとどうなるのか予測する
の3段階に分けて考えるらしい。
ほぼここから引用
https://ja.wikipedia.org/wiki/シチュエーションアウェアネス
参考文献
https://www.logos.t.u-tokyo.ac.jp/~yokoyama/fi-rinko/cgi-bin/upload/takeuchi.pdf
http://www.interaction-ipsj.org/archives/paper2009/interactive/0097/0097.pdf
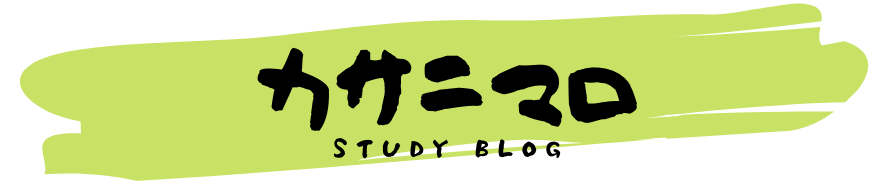
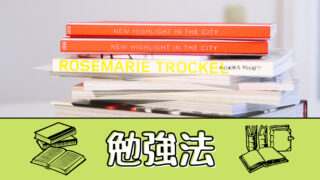


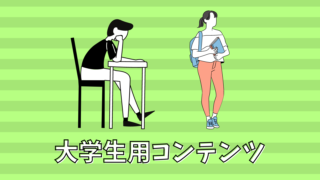



コメント